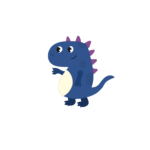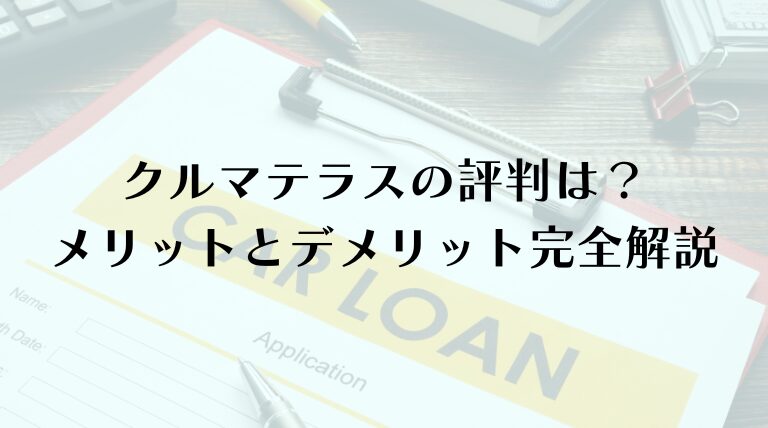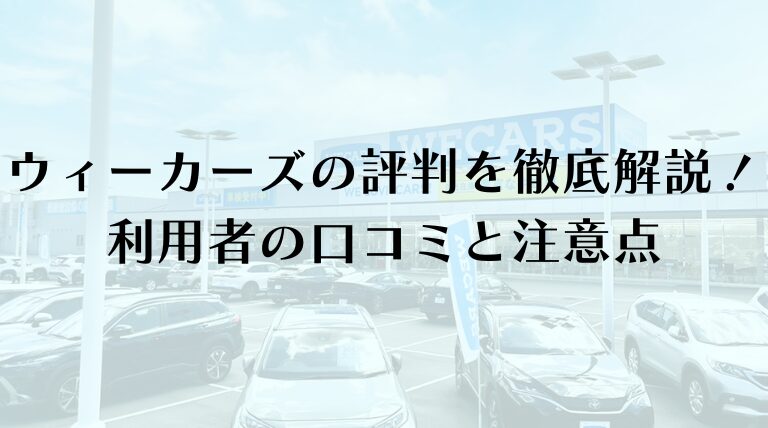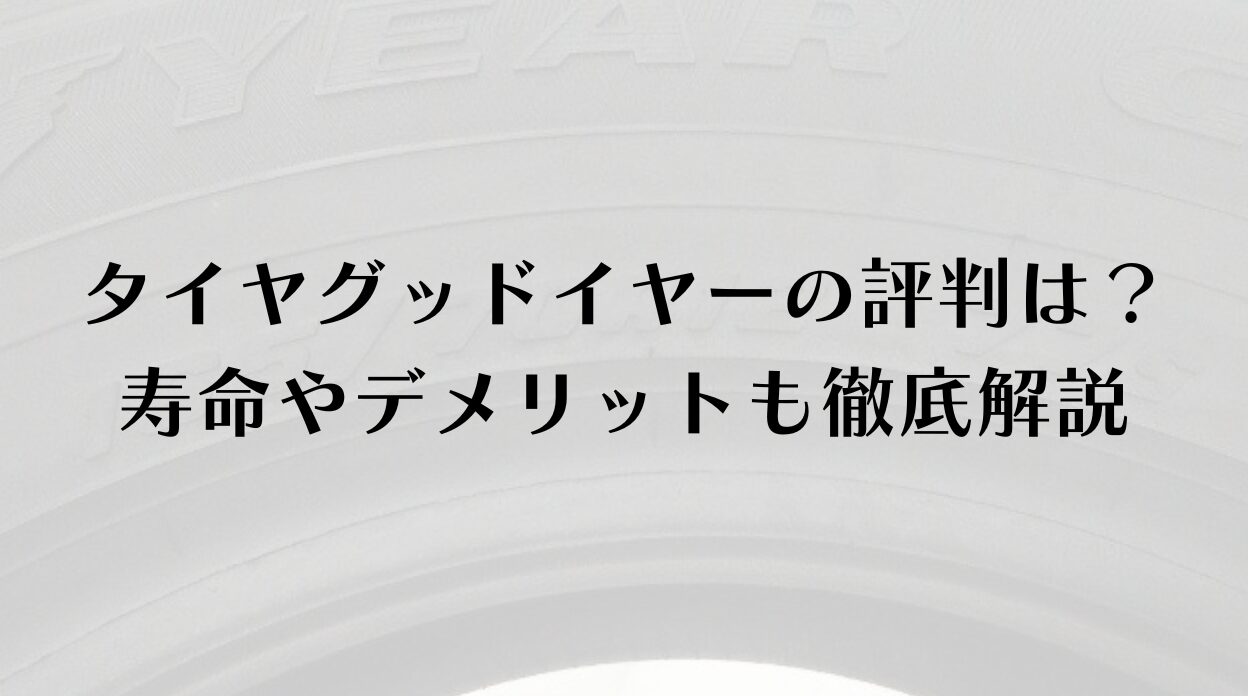なぜBYDは日本で売れない?5つの理由と今後の展望、販売台数や撤退の噂も
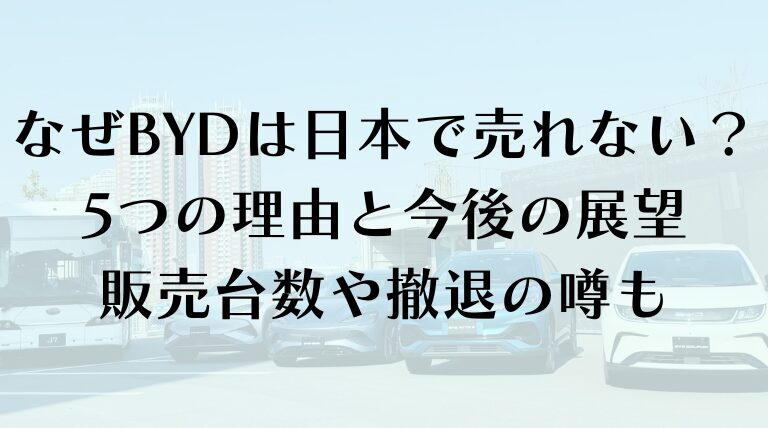
世界で急速に成長するEVメーカーBYD。しかし、日本では「販売が伸び悩んでいるのでは?」という声も聞かれます。実際のところ、日本での販売台数はどうなっているのでしょうか。
世界市場での圧倒的な実績と比べると、確かに日本での普及はこれからという状況です。なぜ日本では苦戦しているのか、その理由を探るとともに、品質や価格、そして一部で囁かれる「撤退」の噂についても気になるところです。
「一体いつ本格的に普及するのか、それとも撤退してしまうのか…」そんな疑問を持つ方もいるかもしれません。この記事では、最新のデータや市場の状況を踏まえ、BYDの日本における現在地と今後の展望を詳しく解説していきます。
- BYDの日本での販売状況と実績
- 世界と日本での販売規模の大きな差
- 日本でBYDが苦戦する複数の要因
- BYDの日本市場への継続的な取り組み
BYDは日本で売れない?販売台数から見る現状

「BYDは日本で売れない」という声を耳にすることが増えましたが、実際のところはどうなのでしょうか。世界市場、特にEV先進国の中国では驚異的な販売台数を記録しているBYDですが、日本市場での実績は異なる様相を見せています。
ここでは、最新の販売台数データや輸入EV市場におけるシェア、世界での販売状況と比較しながら、BYDが日本市場でどのような状況にあるのか、客観的な数字をもとに現状を詳しく見ていきましょう。
日本でのBYD販売台数の推移は?
BYDは2023年1月に乗用車「ATTO 3」を発売し、日本市場へ本格参入しました。参入初年度の2023年における年間の販売台数は1446台と報告されています。
翌2024年には、「DOLPHIN」「SEAL」といった新モデルを相次いで投入し、販売台数は年間で2223台まで増加しました。これは前年比で約58%増という高い伸び率を示しており、月平均では約185台を販売した計算になります。日本自動車輸入組合(JAIA)の統計によると、この年のBYDは輸入乗用車ブランドの中で14位にランクインしました。
しかし、2025年に入ると、1月に新車の日本向け輸出を一時停止した影響もあり、1-2月の累計販売台数は215台と、前年の同じ時期に比べて32%減少しました。2月単月では173台を販売し、前年同月比では44%増となりましたが、輸入車市場でのシェアや順位は前年と同じ水準に留まっています。
BYDは今後、2025年末までに日本国内の販売店舗を100店舗まで増やす計画を発表しており、さらなる販売拡大を目指しています。
世界と日本市場での販売台数の違い
BYDの世界全体での販売台数と日本市場での販売台数には、非常に大きな差があります。
世界市場において、BYDは驚異的な成長を遂げています。2023年には年間約302万台を販売し、世界の自動車メーカー販売台数ランキングでトップ10入りを果たしました。さらに2024年には、前年から約41%増となる約427万台を販売し、ホンダや日産といった日本の大手メーカーの年間販売台数を初めて上回る規模にまで成長しました。特にプラグインハイブリッド車(PHEV)の販売が好調で、世界の新エネルギー車(NEV)市場をリードする存在となっています。
一方、日本市場での販売台数は、2024年実績で年間2223台に留まっています。これは世界販売台数と比較するとごくわずかな数字です。BYDの世界販売の大部分は依然として中国国内が占めており、海外への輸出も増加傾向にはありますが、日本での販売規模はまだ小さいのが現状です。
世界で年間400万台以上を売り上げる巨大メーカーであるBYDですが、日本市場においては、まだ本格的な普及には至っていないと言えます。
輸入EV市場でのシェアと順位
日本の輸入車市場において、BYDは徐々に存在感を増しています。2023年には年間販売台数1446台で輸入車ブランド中17位でしたが、2024年には販売台数を2223台に伸ばし、順位も14位へと上昇させました。この年の輸入乗用車全体に占めるBYDのシェアは約0.99%となり、前年の0.59%から着実にシェアを拡大しています。
電気自動車(EV)に限定して見ると、日本の輸入EV市場は拡大傾向にあります。2024年度には輸入EVの台数が過去最高を記録し、輸入車全体の1割以上をEVが占めるようになりました。この輸入EV市場の中で、BYDは一定の地位を築きつつあります。
ある調査では、2024年の輸入バッテリーEV(BEV)市場において、BYDは約9.2%の比率を占めたと報告されています。また、日本で販売されているBYDの3車種(ATTO 3, DOLPHIN, SEAL)は、いずれも国内の輸入EV販売台数ランキングでトップ10に入っているとも言われています。
ただし、直近の2025年2月のデータでは、輸入乗用車市場全体でのシェアは0.9%、順位は14位と、前年同月と同じ水準に留まっており、今後の動向が注目されます。
中国国内や海外での販売実績
BYDの販売実績は、中国国内市場で特に圧倒的な強さを見せています。2024年の世界販売台数約427万台のうち、その大部分は中国国内で販売されたものです。中国では、政府による新エネルギー車(NEV)普及政策の後押しもあり、BYDは電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド車(PHEV)の販売台数でトップクラスのシェアを誇っています。
2024年には、長年首位を守ってきた上海汽車集団を抜き、中国市場で初めて年間販売台数トップになることが確実視されるなど、その勢いはとどまるところを知りません。手頃な価格と性能のバランスが評価され、一般消費者だけでなく公共交通機関などにも広く採用されています。
一方で、海外市場での販売も急速に拡大しています。2024年の海外販売台数は約42万台に達し、前年から大幅に増加しました。これはBYDの世界販売全体の約1割に相当します。現在、BYDは世界6大陸70カ国以上で車両を販売しており、特にタイ、ブラジル、オーストラリアといった市場で着実に販売を伸ばしています。
欧州市場でも、低価格と性能を武器にシェアを拡大しつつあります。生産拠点も東南アジア、欧州、南米などに展開を進めており、グローバルメーカーとしての地位を固めようとしています。中国国内に比べると海外での販売比率はまだ低いものの、その成長スピードは目覚ましいものがあります。
なぜBYDは日本で売れないと言われる?理由と撤退の噂

BYDの日本での販売が伸び悩んでいる背景には、一体どのような理由があるのでしょうか。単に「売れない」というだけでなく、そこには日本特有の市場環境や消費者心理、ブランドイメージ、価格設定、そしてサービス体制など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
さらに、一部で囁かれる「日本市場からの撤退」の噂についても気になるところです。ここでは、BYDが日本で苦戦している具体的な理由と、撤退の噂の真相について掘り下げていきます。
日本市場特有の壁:国産ブランド信仰
日本の自動車市場では、長年にわたりトヨタ、ホンダ、日産といった国内メーカーが強いブランド力を築き上げてきました。多くの日本人にとって、これらの国産ブランドは単なる移動手段を提供するだけでなく、「品質への信頼」や「安心感」の象徴となっています。
車は高額な買い物であり、長く使うものであるため、実績があり、身近なディーラーでサポートを受けられる国産メーカーを選ぶ傾向が非常に強いのです。
このような市場環境の中で、2023年に本格参入したBYDは、まだ「新しいブランド」という認識です。性能や価格面で魅力があったとしても、「よく知らないメーカーの車に数百万円を出すのは不安」「周りに乗っている人がいないから、実際のところがわからない」と感じる消費者は少なくありません。
特に、車は命に関わる製品でもあるため、実績や評判が確立されていないブランドに対しては、どうしても慎重になってしまいます。この「ブランドへの信頼」という見えない壁が、BYDが日本で販売を伸ばす上での大きな課題となっています。
「中国製」へのイメージと品質への懸念
BYDが日本市場で苦戦するもう一つの理由として、「中国製品」に対する一部の消費者が持つ先入観やイメージが挙げられます。
「安かろう悪かろう」といった過去のイメージや、品質、安全性に対する漠然とした不安感が、購入をためらわせる一因となっているようです。自動車は高価な買い物であり、安全性も非常に重要視されるため、消費者が慎重になるのは当然とも言えます。
BYDの車は、欧州の自動車安全テスト「ユーロNCAP」で最高評価の5つ星を獲得するなど、客観的な安全性能は高く評価されています。しかし、そうした事実情報だけでは、長年培われてきた「中国製」に対するイメージを完全に払拭するのは難しい面があります。
特に年配の層を中心に、品質に対する不信感が根強く残っている可能性も指摘されています。BYDとしては、製品の品質や安全性をアピールし続けるとともに、日本市場での実績を積み重ねていくことで、こうしたイメージを少しずつ変えていく必要があるでしょう。
日本のEV普及率と充電インフラの問題
日本における電気自動車(EV)の普及は、欧米や中国と比較して遅れています。2023年の新車販売におけるEVの割合(軽自動車を除く)は約1.7%に留まっており、まだガソリン車やハイブリッド車が主流です。この背景には、いくつかの要因がありますが、特に大きな課題とされているのが充電インフラの整備状況です。
政府は2030年までに公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを30万口設置するという目標を掲げていますが、2024年3月時点での設置数は約3.2万口と、目標には遠く及ばないのが現状です。
自宅に充電設備を設置できない集合住宅の住民や、長距離移動時の充電切れ(電欠)に対する不安から、EVの購入をためらう人は少なくありません。
また、充電スタンドが見つかっても、先客がいて使えなかったり、充電に時間がかかったりするケースもあります。EVを主力とするBYDにとって、日本の充電インフラの整備状況は、販売拡大における大きなハードルの一つとなっています。
販売ディーラー網とアフターサービス体制
BYDは日本市場への本格参入から日が浅いため、販売・サービス拠点の整備がまだ十分とは言えません。2024年3月時点で、正規ディーラー店舗数は全国に約51店舗となっており、これは国内大手メーカーの店舗数と比べるとかなり少ない数字です。
BYDは2025年末までに100店舗体制を目指してネットワークを拡充中ですが、現状では「近くに店舗がない」「購入後のメンテナンスや修理をどこで受けられるのか不安」と感じる消費者が多いようです。
アフターサービスについては、車両本体の保証に加え、EVの重要な部品であるバッテリーに対して8年または16万kmという長期保証を提供しています。これはテスラや日産リーフと同等以上の手厚い保証内容です。
また、24時間365日対応のロードサイドアシスタンスや、BYD車を熟知したスタッフによるメンテナンス体制も整えています。
しかし、いくら保証やサポート体制が充実していても、実際にサービスを受けられる拠点が近くになければ、ユーザーの不安を完全に解消することは難しいでしょう。販売網とサービス網の拡充は、BYDが日本で信頼を獲得するための喫緊の課題と言えます。
価格設定は本当に競争力があるのか?
BYDの車両価格は、同クラスのEVと比較して競争力があると言われています。特に、2025年4月には主力モデルである「ATTO 3」と「DOLPHIN」の大幅な値下げが発表されました。
ATTO 3は約32万円値下げされて418万円に、DOLPHINはエントリーグレードとして「Baseline」が新設され、実質的に約64万円値下げとなる299.2万円(税込み)から購入可能となりました。国の補助金などを活用すれば、さらに購入費用を抑えることができます。
この価格設定は、競合する輸入EVや、一部の国産EVと比較しても魅力的な水準です。しかし、日本の自動車市場全体で見ると、依然として手頃な価格のガソリン車やハイブリッド車の人気が高く、補助金を考慮しない場合の車両価格だけを見ると、「まだ高い」と感じる消費者もいるかもしれません。
また、価格の安さだけで購入を決めるのではなく、ブランドへの信頼感、デザインの好み、アフターサービス体制なども含めて総合的に判断するユーザーが多いのが日本の特徴です。BYDとしては、価格競争力に加えて、製品の魅力や信頼性をより一層アピールしていく必要があります。
BYD日本撤退の噂は本当?いつ頃?
インターネット上などで、「BYDは日本から撤退するのではないか?」といった噂が見られることがあります。これは、世界市場での好調さとは対照的に、日本での販売台数が伸び悩んでいる状況や、「中国メーカーだから」といったイメージから来る憶測などが背景にあると考えられます。
しかし、現時点でBYDが日本市場からの撤退を計画しているという公式な情報や具体的な根拠はありません。むしろ、BYDは日本市場を重要視している姿勢を示しています。2025年末までに販売拠点を100店舗に拡大する計画を進めているほか、2025年4月には主力車種の大幅な値下げを実施し、販売攻勢を強めています。
さらに、日本市場向けに新たなモデルの投入も予定されています。これらの動きを見る限り、BYDは短期的な販売不振で諦めるのではなく、長期的な視点で日本市場に根付こうとしていると考えられます。
「いつ頃撤退するのか?」という問いに対しては、現時点では「撤退の予定はなく、むしろ事業を拡大しようとしている」と答えるのが適切でしょう。今後の販売動向や市場戦略が注目されます。
まとめ:BYDは日本で売れない理由について
- 2024年の日本年間販売台数は2223台で前年比約58%増であった
- 2025年初頭の販売は前年同期比で減少したが2月単月は増加した
- 2025年末までに国内販売店100店舗を目指している
- 世界販売台数と日本販売台数には極めて大きな差がある
- 2024年の世界販売は約427万台で日本の大手メーカーを超えた
- 日本の輸入車市場でのシェアは約1%で順位は14位(2024年)である
- 輸入EV市場では約9.2%のシェアを持つとの調査もある(2024年)
- 中国国内市場では圧倒的な販売実績を誇る
- 海外販売も急拡大し世界70カ国以上で展開している
- 日本では国産ブランドへの信頼が厚いことが参入障壁である
- 一部消費者に「中国製品」への先入観や品質懸念が存在する
- 日本のEV普及率は低く充電インフラ整備が課題である
- 国内販売ディーラー網はまだ少なく拡充中である
- バッテリーには8年16万kmの長期保証が付帯する
- 2025年4月に主力モデルの大幅値下げを実施した
- 日本市場からの撤退予定はなく事業拡大を目指している