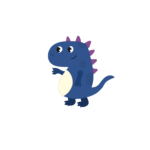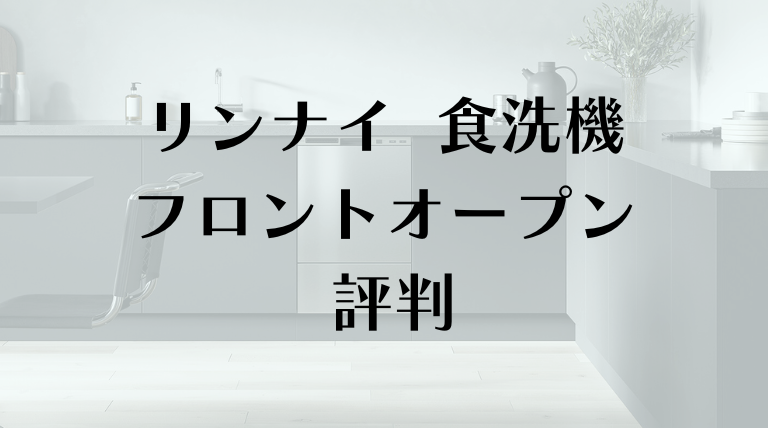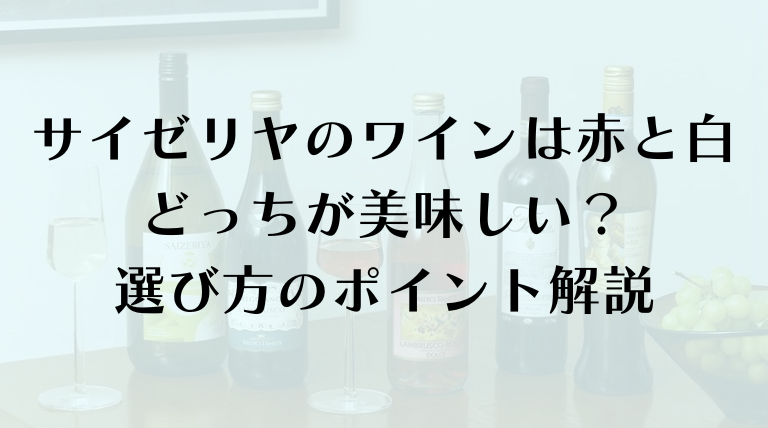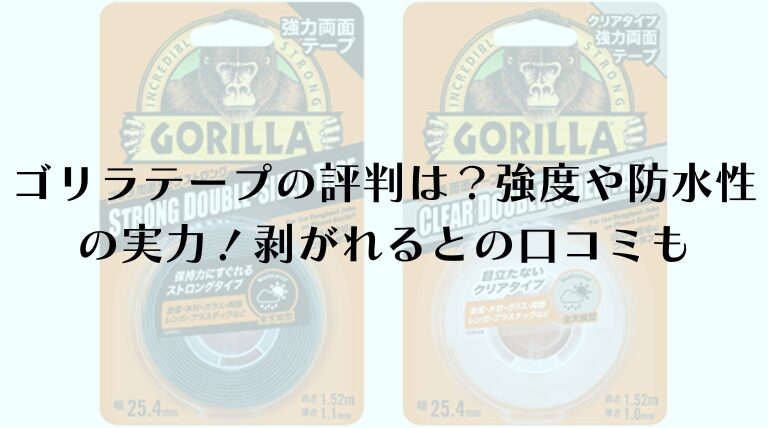隈研吾の建築はやばい?腐る木材とデザインへの不評・批判を検証
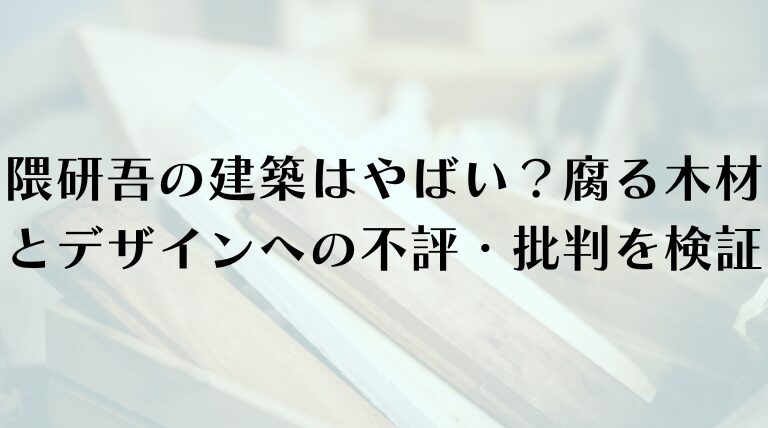
著名な建築家である隈研吾氏について、インターネット上では様々な評判が飛び交っています。その中には、氏の手がけた建築物に対し、「木材が腐るのではないか」「早くもボロボロになっている」といった、気になる声も少なくありません。
実際に、一部の建築物では木材の腐食が報告されており、耐久性への懸念から不評の声も上がっている状況です。また、デザイン手法や仕事の進め方に対しても、様々な意見が見られます。
この記事では、なぜ隈氏に関してこのような厳しい評判が立つのか、建築物の具体的な状態や寄せられる批判、そして隈氏自身の考え方などを詳しく解説し、その真相に迫ります。
- 隈研吾建築の木材劣化の具体的事例
- 建築物が劣化する主な理由や背景
- 隈氏のデザインや仕事への批判内容
- 劣化問題に対する隈氏自身の見解
隈研吾はやばい?建築物が腐る・劣化する評判の真相
建築家・隈研吾氏の名前を検索すると、「やばい」という言葉を目にすることがあります。特に、氏が手掛けた建築物については、木材が「腐る」「劣化が早い」といったネガティブな評判も聞かれる状況です。これは一体どういうことなのでしょうか。
ここでは、実際に劣化が指摘されている美術館や市役所、新国立競技場などの事例を具体的に挙げながら、隈研吾氏の建築物が「やばい」と言われる評判の真相を探っていきます。
なぜ?隈研吾建築が「腐る」と言われる理由
隈研吾氏設計の建築物で木材が「腐る」と言われる背景には、いくつかの理由が考えられます。主な要因として、木材の選定や使い方、日本の気候特性、そして維持管理の問題が挙げられます。木材は、本来、水分や湿気に弱い性質を持っています。
そのため、特に雨風に直接さらされる屋外、例えば外壁や屋根などに使用する場合は、水に強い種類の木材を選んだり、適切な保護塗装を施したりすることが重要になります。
建築の専門家の中には、隈氏のデザインにおいて、コスト面の制約などからか、本来内装用とされるような水濡れに弱い木材(薄い板を重ねた合板など)を、十分な防水処理をせずに外装に使っているケースがあると指摘する声があります。
また、格子状のルーバーデザインは見た目に美しい一方で、雨掛かりしやすく、木材にとっては過酷な環境となりがちです。日本の高温多湿な気候も、木材の腐食やカビの発生を促進する一因と言えるでしょう。隈氏自身も、大規模な木造建築はまだ歴史が浅く、試行錯誤の段階であると述べています。
栃木:美術館の木材が腐食し改修へ
栃木県那珂川町にある「馬頭広重美術館」は、隈研吾氏が設計を手掛けた代表的な建築物の一つです。しかし、この美術館で木材の深刻な腐食が進み、大規模な改修が必要な事態となっています。
2000年に開館したこの美術館は、地元産の「八溝杉(やみぞすぎ)」を格子状に組んだ「ルーバー」と呼ばれるデザインが特徴で、周囲の自然に溶け込む美しい外観が評価されてきました。
ところが、開館から数年が経過した頃から劣化が目立ち始め、特にここ4~5年は、屋根や壁に使われている杉材の黒ずみ、腐食、折れ曲がりなどが急速に進行している状況です。原因としては、雨風に長期間さらされ続けたことや、建設当時に使われた木材保護塗料の性能が現在ほど高くなかったことなどが挙げられています。
改修には約3億円もの費用が見込まれており、町ではふるさと納税やクラウドファンディングを活用して資金調達を進めている状況です。専門家からは、雨の影響を受けやすい場所に杉材を使ったデザイン自体の問題や、予算的な制約があった可能性も指摘されています。
群馬:市役所の木材もボロボロに腐食か
群馬県富岡市の市庁舎でも、隈研吾氏設計の建築物における木材劣化の問題が指摘されています。この市庁舎は2018年に完成した比較的新しい建物ですが、完成からわずか6年ほどで、外装に使用されている木材の一部に腐食のような劣化が見られるというのです。
具体的には、庁舎のひさしの裏側に使われている木材の一部が腐食しているように見え、窓を覆うように設置された木製のルーバー(羽板)にも変色が進んでいることが確認されました。
市の調査によると、特に劣化が見られたのは、不燃薬剤が注入された合板が使われている軒裏部分でした。この不燃薬剤が塗料を溶かし、取り付け金具などの鉄部を腐食させたことが原因ではないかと考えられています。
さらに、サビによって金具が膨張し、雨水の排水を妨げた結果、軒裏の合板に雨染みが広がった可能性も指摘されています。この問題はSNSでの指摘をきっかけに明らかになり、現在、修繕に向けた協議が進められています。なお、市によると、これらの劣化が建物の構造的な強度に影響を与えるものではないとのことです。
新国立競技場も劣化の懸念
2019年に完成した東京の新国立競技場。隈研吾氏が設計に携わったこの建物も、木材を多用したデザインが特徴ですが、その木材部分の長期的な耐久性について懸念の声が上がっています。特に、スタジアムの外周を覆う軒庇(のきびさし)や屋根の骨組みなど、外部に露出している木材の劣化が心配されている状況です。
一部の報道や専門家からは、完成から数年しか経っていないにも関わらず、すでに木材の黒ずみやひび割れといった劣化の兆候が見られるとの指摘があります。中には、20年後には大規模な改修が必要になるのではないか、という予測も出ています。
これに対し、設計に関わった隈研吾建築都市設計事務所や建設を担当した共同企業体は、使用している木材には国の基準に沿った適切な防腐処理が施されており、50年から60年は交換の必要がないとの見解を示しています。
構造的な耐久性については問題ないとする専門家もいますが、外観、特に雨風にさらされる部分の見栄えが将来的に悪くなる可能性は否定できないようです。
全国各地の建築物でも同様の問題
隈研吾氏が設計した建築物における木材の劣化問題は、これまで見てきた栃木県の美術館や群馬県の市役所に限りません。実は、全国各地にある氏の作品で、同様の現象が報告されています。
例えば、東京都八王子市にある京王線高尾山口駅の駅舎では、完成から9年ほどで柱部分にカビが発生し、黒ずみが目立っていると言われています。
また、山形県の銀山温泉にある旅館「藤屋」や、高知県梼原(ゆすはら)町の「雲の上のホテル」といった、木材をふんだんに使用したデザインが特徴の建物でも、湿気による劣化や老朽化が課題となっています。「雲の上のホテル」の本館に至っては、完成からわずか27年で取り壊され、建て替え工事が行われました。
新潟県長岡市の「アオーレ長岡」なども含め、これらの事例は、木材を多用するデザインの美しさの裏側にある、維持管理の難しさやコストの問題を私たちに示唆していると言えるでしょう。特に税金で賄われる公共建築においては、長期的な視点での耐久性やメンテナンス計画がより重要になってきます。
隈研吾はやばい?不評や批判の背景にあるもの
隈研吾氏が「やばい」と評される理由は、前述の建築物の劣化問題だけにとどまりません。一部では、氏のデザイン手法や仕事の進め方そのものに対しても、批判的な声が存在するのです。
例えば、特徴的なデザインが揶揄されたり、膨大な仕事量やメンテナンスコストを疑問視する評判も見受けられます。ここでは、こうした不評や批判がなぜ生まれているのか、その背景にある様々な要因について詳しく解説いたします。
デザインへの評判:「クマちゃんシール」との揶揶
隈研吾氏のデザイン、特に木製のルーバー(格子状の部材)などを多用するスタイルは、一部の建築専門家などから「クマちゃんシール」と揶揄されることがあります。
これは、一見すると特徴的で魅力的なデザイン要素が、まるで既製のシールを貼り付けるかのように、様々な建築プロジェクトで繰り返し用いられているように見える、という批判的な見方から生まれた言葉です。大量の設計依頼を効率的にこなすために、ある種の記号的なデザインパターンを多用しているのではないか、というわけです。
この「シール」に例えられるデザイン手法は、個々の建築物が持つべき固有性や、その場所ならではの文脈との関連性が薄れているのではないか、という疑問を投げかけています。言い換えれば、どこに建てても同じような印象を与えかねない、という指摘でもあります。
もちろん、デザインの評価は主観的な側面も大きいですが、このような揶揄が生まれる背景には、隈氏の圧倒的な仕事量と、その中で確立されたデザイン手法に対する、専門家ならではの厳しい視線があると考えられます。
木の使い方は「デコレーション」?専門家の不評
隈研吾氏の建築における木材の用い方について、一部の専門家からは「デコレーション(装飾)に過ぎない」といった厳しい不評も聞かれます。これは、構造体として木材の特性を活かすというよりは、建物の表面を覆う化粧材として、見た目の印象を操作するために使われている側面が強いのではないか、という指摘です。
例えば、鉄骨やコンクリート造の建物の表面に、薄い木材やルーバーを取り付ける手法などが、これに該当すると考えられます。
こうした使い方に対しては、木材本来の力強さや構造的な美しさを損なっている、あるいは、単なる「木を使っている感」を演出しているだけではないか、といった批判があります。
前述の通り、外装に本来内装用とされるような木材を使用しているケースが劣化を招いているとの指摘もあり、デザイン優先の姿勢が耐久性やメンテナンス性の問題を軽視しているのではないか、という不評につながっている側面もあるようです。
木材への深い理解に基づいた使い方というよりは、記号的な「木らしさ」の表現にとどまっている、と捉える専門家もいるのです。
仕事のスタイルへの批判的な評判
隈研吾氏の仕事の進め方や、その圧倒的な受注量についても、批判的な評判が存在します。隈研吾建築都市設計事務所は、年間400件以上とも言われる膨大な数のプロジェクトを抱え、約300人のスタッフで対応しているとされます。
この驚異的な仕事量は、隈氏が予算規模の大小に関わらず、様々な依頼を引き受ける姿勢の表れとも言えますが、一方で、個々のプロジェクトに対する設計の質や関与度が低下しているのではないか、という懸念を生んでいます。
また、これだけ多くの仕事が集中する背景には、単にデザイン性が評価されているだけでなく、隈氏が建築界の名門研究室出身であることや、大手ゼネコンとの強いパイプを持っていることなどが影響しているのではないか、と推測する声もあります。
さらに、公共建築において国産材利用が推奨される近年の流れに、隈氏のデザインがうまく合致しているという側面も指摘されています。こうした状況に対し、特定の建築家に仕事が偏りすぎているのではないか、といった批判的な見方も存在します。
メンテナンスコストへの懸念
隈研吾氏が設計する建築物は、木材を多用するなどデザイン性が高い反面、完成後の維持管理にかかる費用、すなわちメンテナンスコストが高くなるのではないかという懸念が常に付きまといます。
特に、屋外に木材を使用する場合、雨風や紫外線による劣化を防ぐために、定期的な塗装や部分的な交換などのメンテナンスが不可欠です。デザインが複雑であればあるほど、その手間や費用は増大する傾向にあります。
前述の通り、那珂川町馬頭広重美術館や富岡市役所など、実際に完成から比較的短い期間で木材の劣化が顕著になり、多額の修繕費用が必要となっている事例は、この懸念を裏付けるものと言えるでしょう。
初期の建設コストだけでなく、長期的な視点でのランニングコストも考慮に入れると、果たしてそのデザインが本当に適切なのか、特に税金で賄われる公共建築においては、より慎重な判断が求められる、というわけです。デザインの魅力と維持管理の負担とのバランスは、建築を評価する上で重要なポイントとなります。
隈氏自身の見解と建築界の反応
これまでに見てきた建築物の劣化問題や、デザイン、仕事のスタイルに対する様々な批判について、隈研吾氏自身はどのように考えているのでしょうか。
インタビューなどでの発言を見ると、氏は大規模な木造建築はまだ20年程度の歴史しかなく、いわば「実験段階」であり、その過程で様々な課題が見えてくるのはある種当然である、という見解を示しています。試行錯誤を繰り返している模索期間なのだ、と述べているのです。
また、木材という素材の特性上、経年劣化は避けられないものであり、一部分だけを切り取って批判的に見るのはフェアではない、とも語っています。一方で、建築界の他の専門家や関係者の中には、これらの劣化問題に対し、「やはりそうなったか」「予想通りだ」といった、ある程度冷ややかな反応も見られます。
これは、デザインや材料選定の段階で、将来的なリスクがある程度予見されていた可能性を示唆しているのかもしれません。当事者の見解と、周囲の受け止め方には、若干の温度差があるようです。
まとめ:隈研吾はやばい?について
- 隈研吾建築には「腐る」「劣化が早い」との評判が存在する
- 木材の選定・使い方・日本の気候・維持管理が劣化の主な要因とされる
- 屋外木材には耐水性の高い種類や適切な保護塗装が重要である
- コスト制約から内装用木材を外装に使用する例が指摘される
- 格子状のルーバーデザインは雨掛かりしやすく木材に過酷な環境である
- 日本の高温多湿な気候が木材の腐食やカビを促進する
- 馬頭広重美術館では木材腐食が進み約3億円の改修が必要となった
- 富岡市庁舎も完成後約6年で外装木材に腐食が見られる
- 新国立競技場の外部木材にも長期的な耐久性の懸念がある
- 全国各地の隈研吾建築で同様の木材劣化問題が報告される
- 木材多用デザインは維持管理の難易度とコストの問題を伴う
- 隈氏のデザイン手法は「クマちゃんシール」と揶揄されることがある
- デザインが記号的で建築の固有性が薄いとの批判が存在する
- 木材の使い方が構造的でなく「デコレーション」に過ぎないとの不評もある
- デザイン優先で耐久性・メンテナンス性を軽視していると指摘される
- 隈事務所の年間400件超という膨大な仕事量に設計の質低下が懸念される
- 仕事の集中には隈氏の経歴やゼネコンとの関係、国産材利用の時流が影響すると推測される
- 特定の建築家に仕事が偏りすぎているとの批判的な見方もある
- 木材多用デザインは初期費用に加えメンテナンスコスト増大の懸念がある
- 隈氏は大規模木造建築を「実験段階」であり試行錯誤の過程だと述べる
- 建築界の一部には劣化問題を「予想通り」と冷ややかに見る反応もある