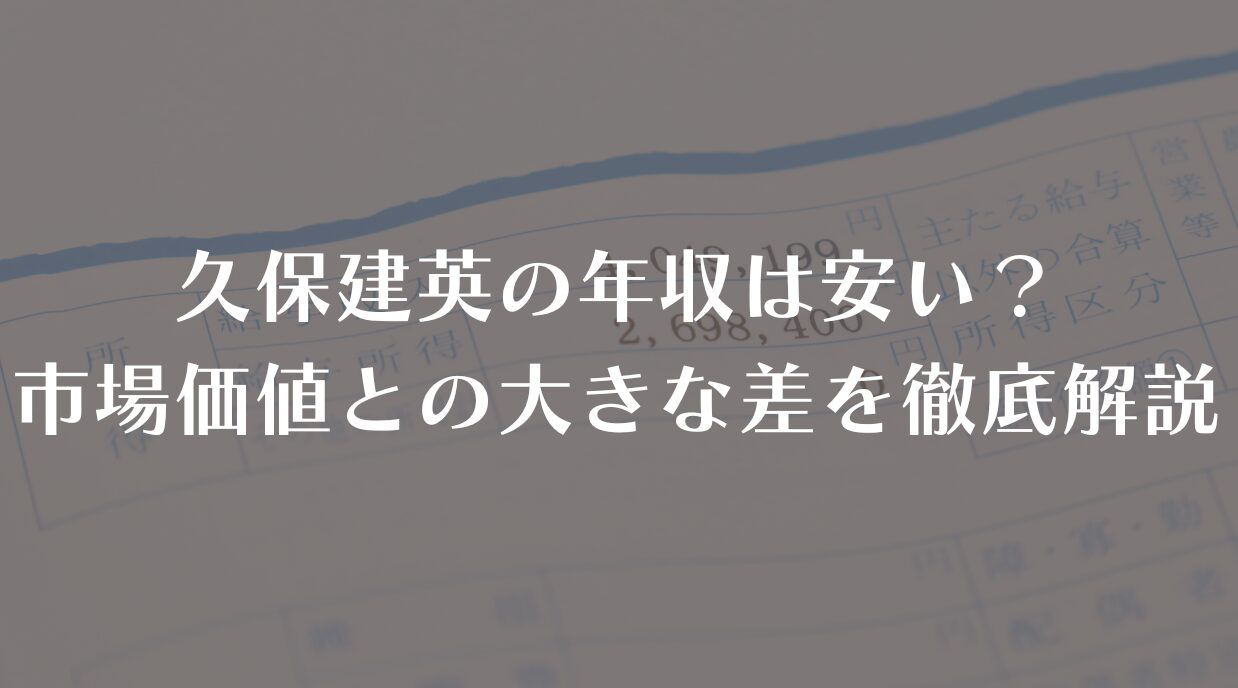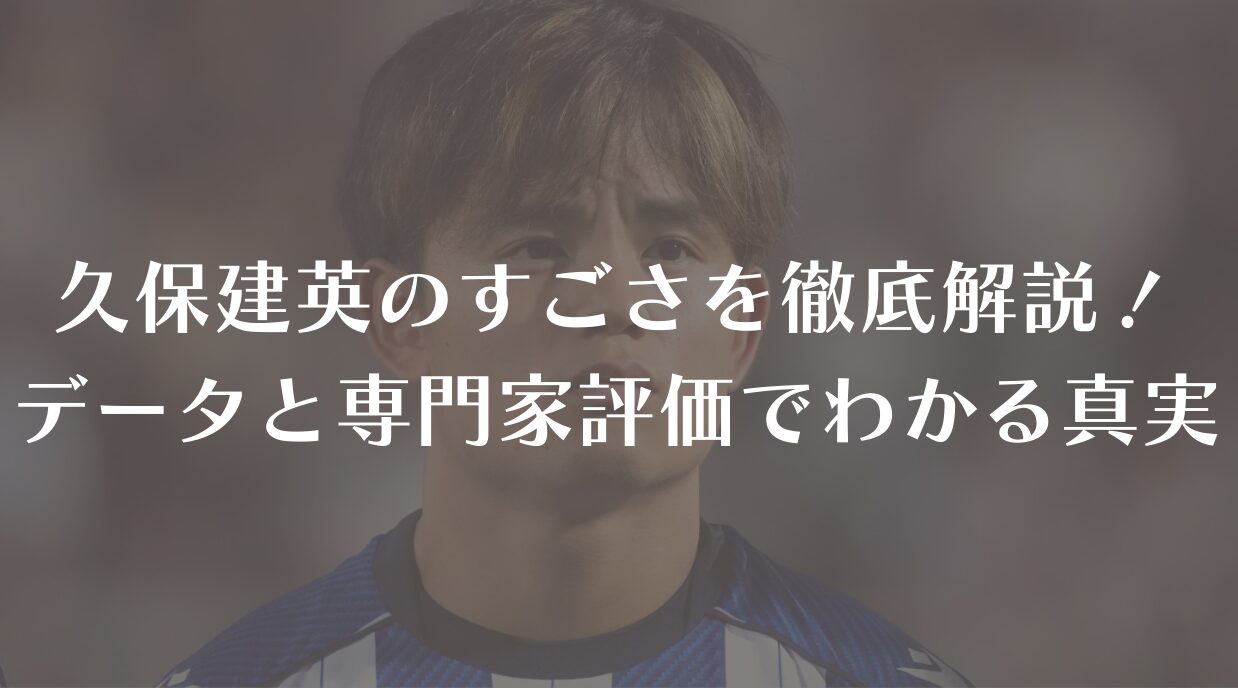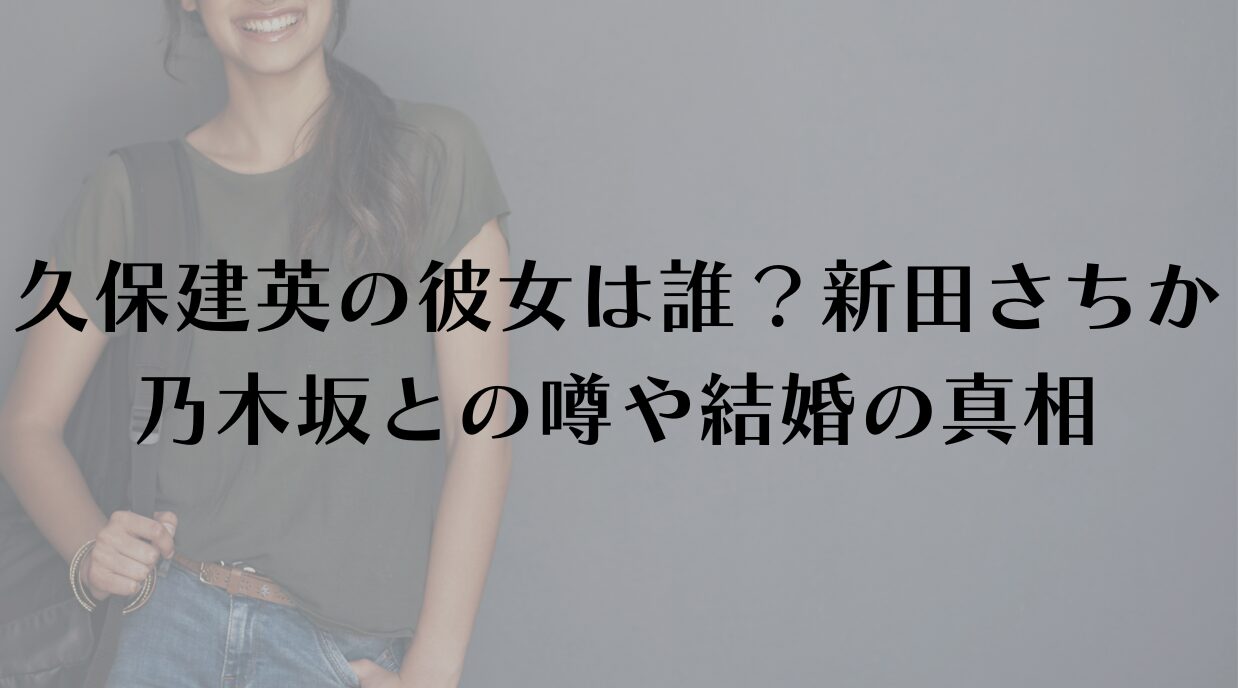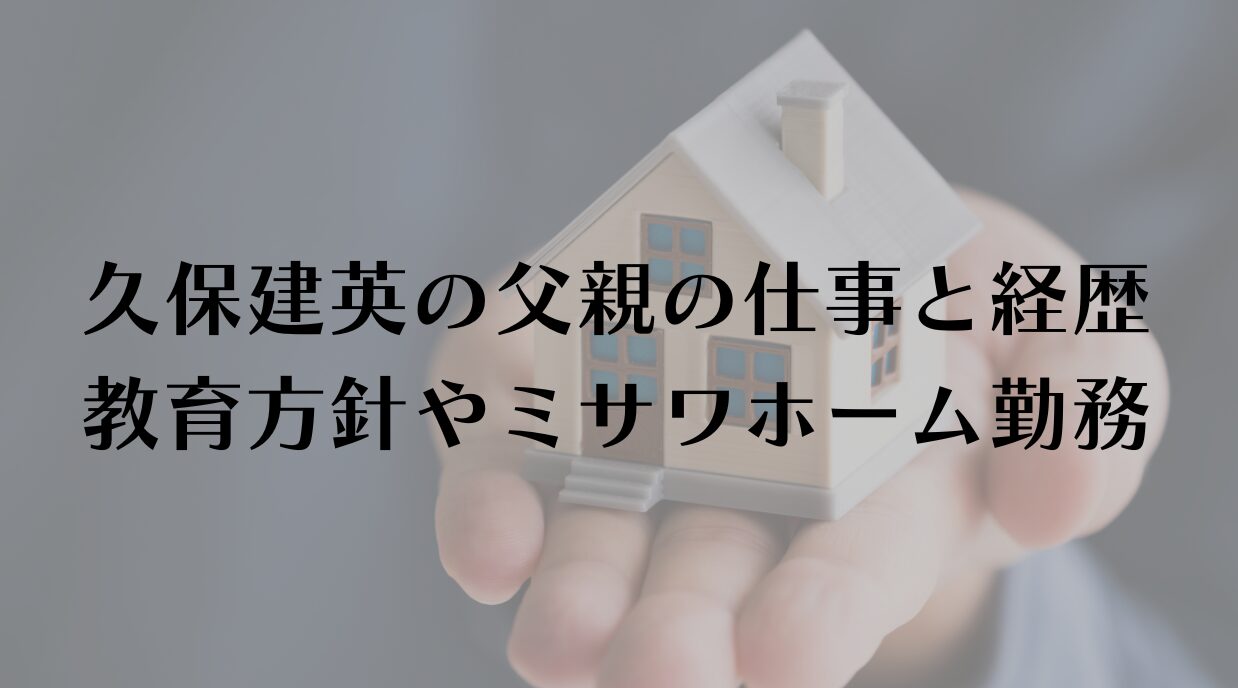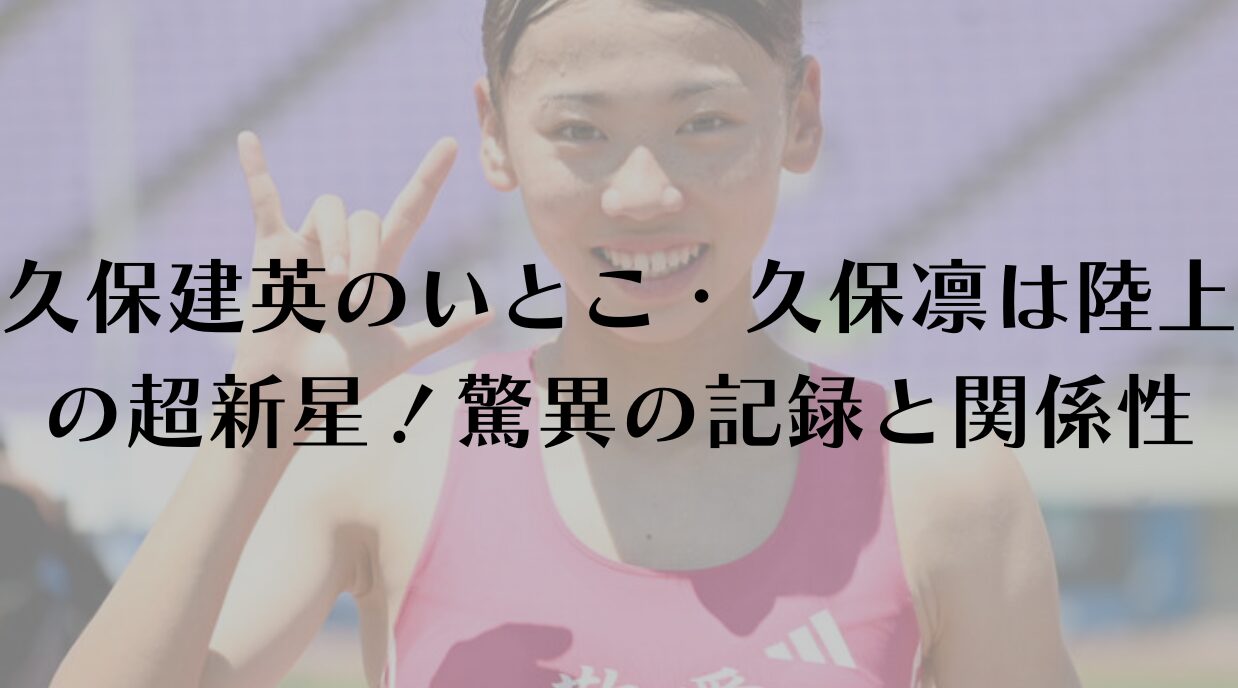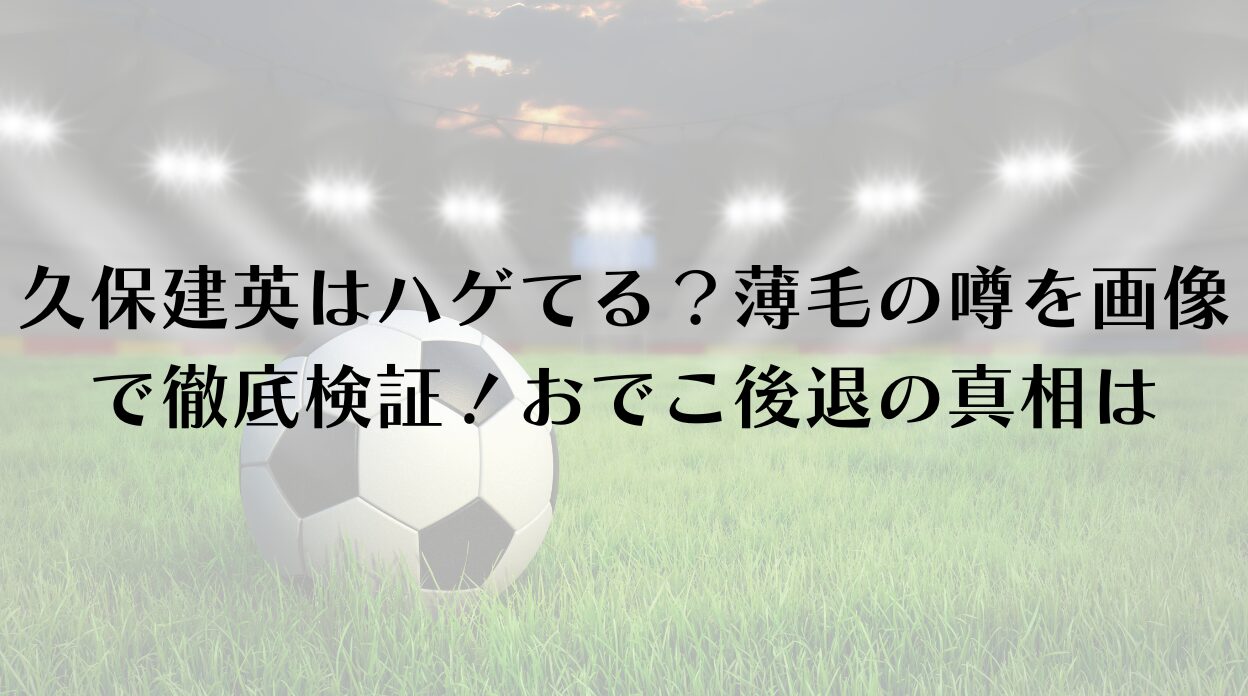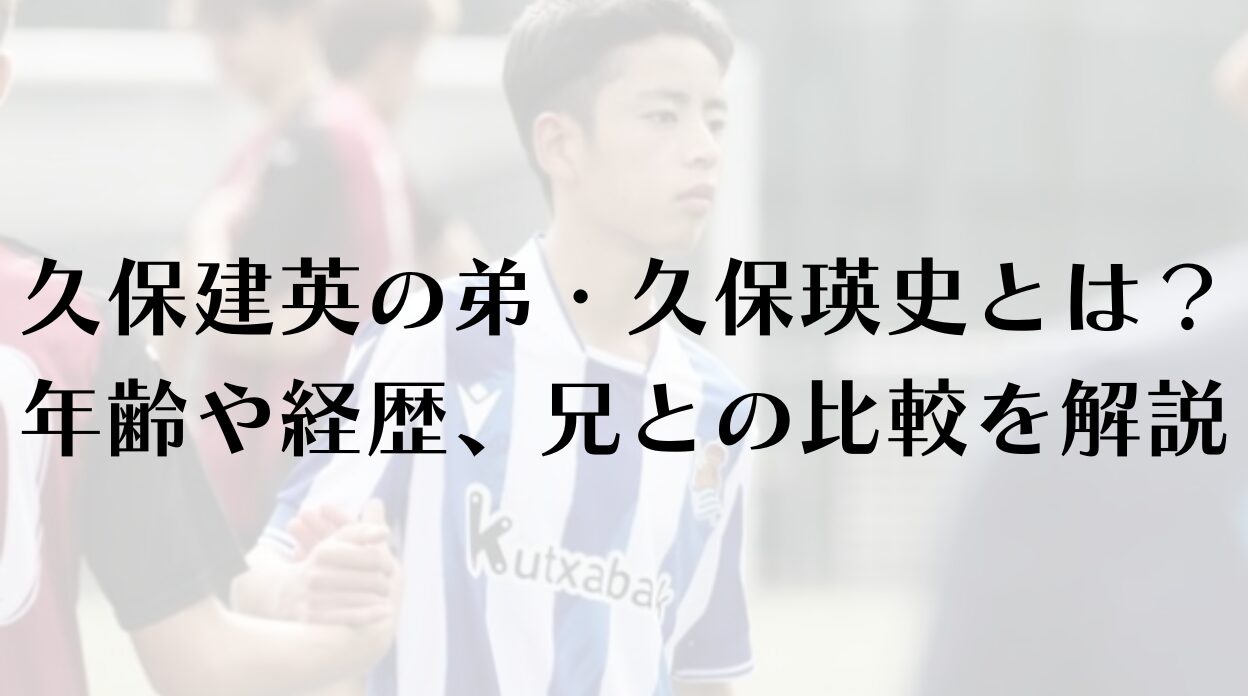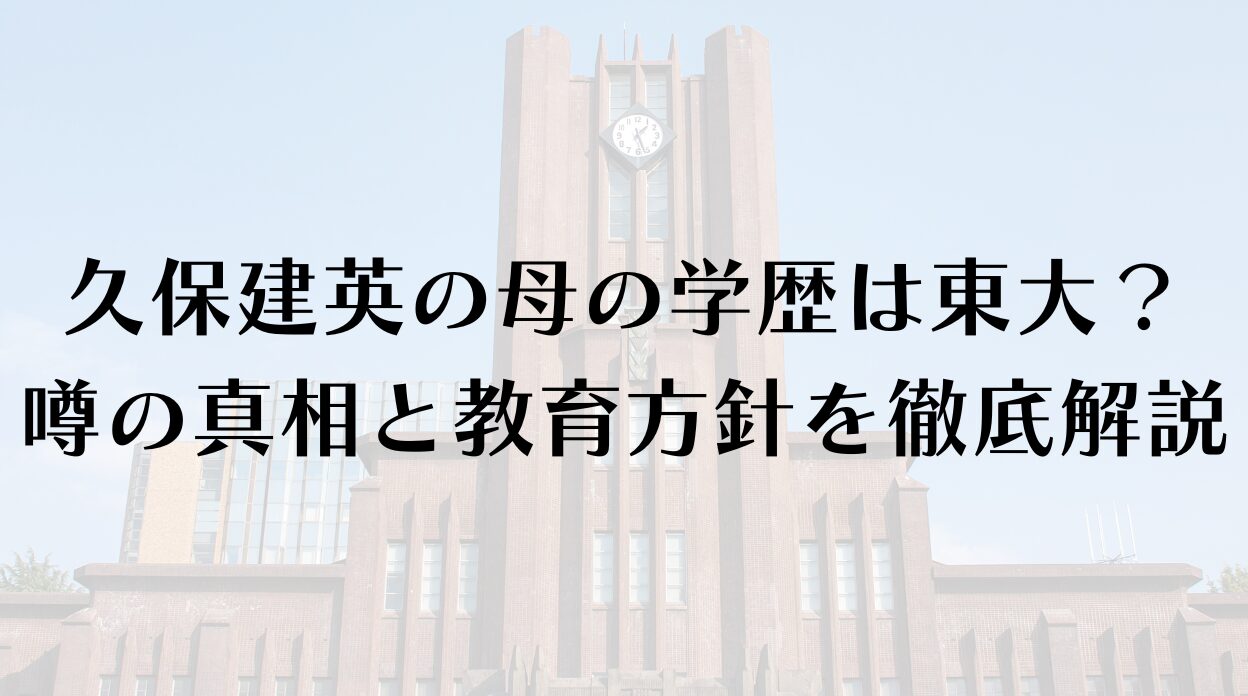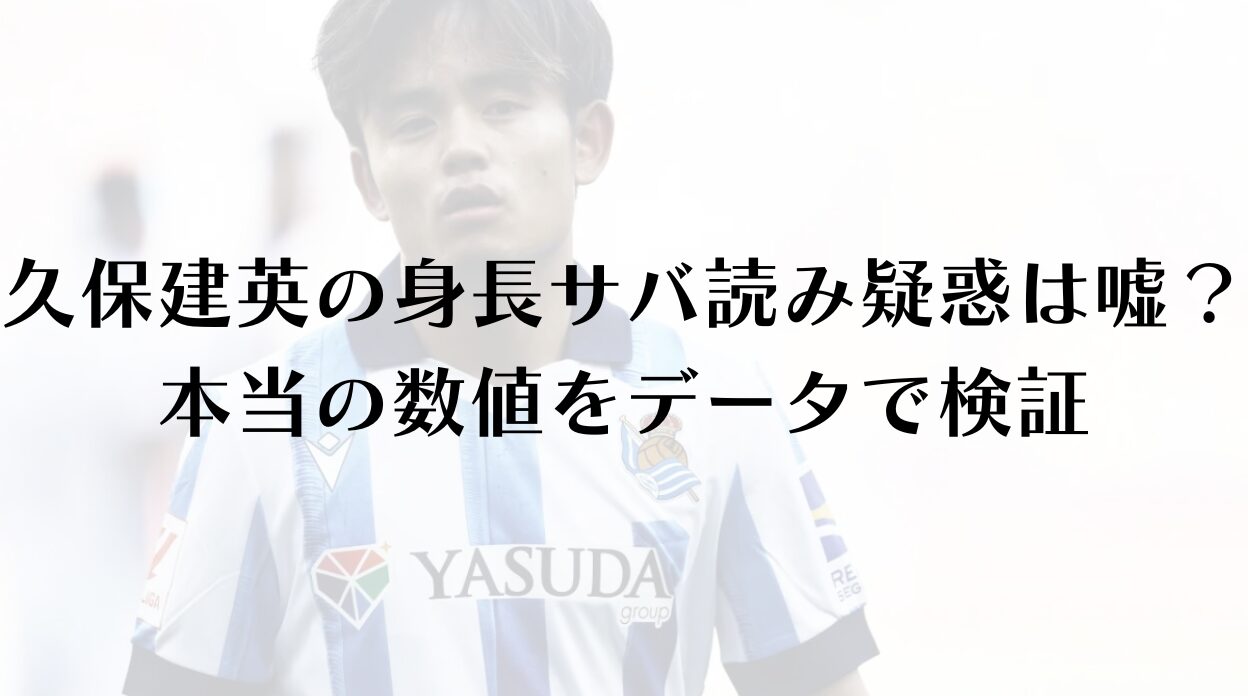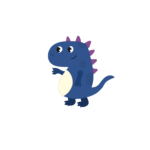久保建英の筋肉はいつから?ガリガリからの肉体改造と驚異の身体能力
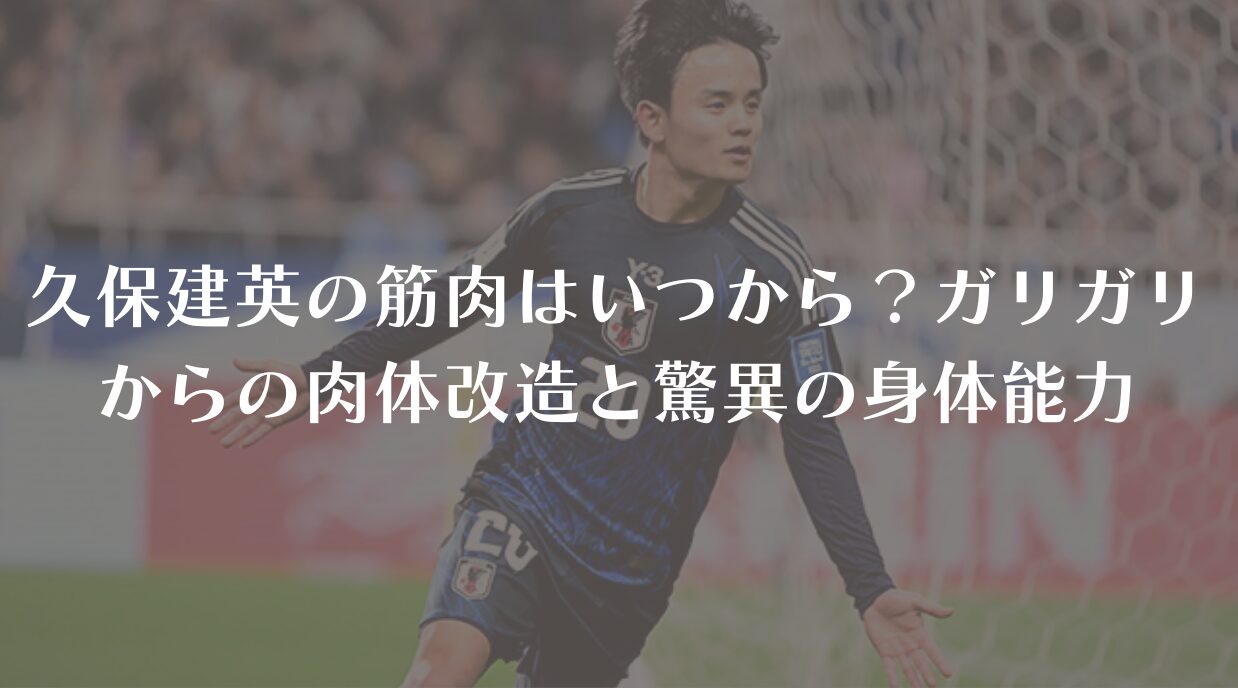
サッカー日本代表として圧倒的な存在感を放つ久保建英選手。彼のプレーを見るたびに、その卓越したテクニックと同時に、強靭なフィジカルに驚かされる方も多いのではないでしょうか。
かつてはガリガリとも言われ、ふくらはぎが細いと指摘されることもあった彼が、今では屈強な海外選手を相手に当たり負けしない姿を見せています。
その裏には、地道な筋トレやフィジカル強化への意識がありました。ベンチプレスなどで鍛え上げた上半身は、彼の高い身体能力を支え、その変化が鋭いキック力にどう影響しているのか、多くのファンが注目しています。
この記事では、久保建英選手の筋肉がいつから進化したのか、その肉体改造の過程と、プレーに与える影響について、多角的な視点から詳しく解説していきます。
- 久保建英選手が肉体改造に取り組んだ背景と具体的な過程
- フィジカル強化のために行っている筋トレやトレーニングの内容
- 強靭な筋肉が実際のプレーの質に与えるポジティブな影響
- デビュー当時から現在までの身体能力の変化と進化の詳細
久保建英の筋肉はいつから進化したのか

- ガリガリと言われたデビュー当時の体格
- ふくらはぎが細いのは本当か?特徴を解説
- スペインで痛感したフィジカルの重要性
- 過酷な筋トレメニューで肉体を改造
- ベンチプレスで鍛え上げた上半身の強さ
- 当たり負けしない体幹トレーニングの成果
ガリガリと言われたデビュー当時の体格
今でこそフィジカルの強さが際立つ久保建英選手ですが、プロデビュー当時は、才能豊かなテクニックとは対照的に、その華奢な体格が注目されることも少なくありませんでした。特に、海外の屈強なディフェンダーと比較すると、線が細く「ガリガリ」という印象を持ったサッカーファンもいたと考えられます。
実際に、10代で世界のトップリーグに挑戦し始めた頃は、相手選手との接触プレーで体勢を崩されたり、ボールを失ったりする場面が見受けられました。これは、単に体重が軽いというだけでなく、プロの世界で戦い抜くための筋量や体幹の強さが、まだ発展途上であったことを示しています。
もちろん、彼の持ち味である俊敏性やテクニックは当時から世界レベルでしたが、フィジカル面が今後の大きな課題であることは明らかでした。このデビュー当時の経験が、後の本格的な肉体改造へと繋がる重要な原点となったのです。
ふくらはぎが細いのは本当か?特徴を解説
久保建英選手の身体的特徴として、「ふくらはぎが細い」という点がしばしば話題に上ります。実際に映像や写真を見ると、他のサッカー選手と比較して、ふくらはぎがすっきりしているように見えるかもしれません。しかし、これは一概に筋力不足を意味するわけではないのです。
見た目と機能性の違い
サッカー選手に必要なのは、単に太く大きな筋肉ではありません。特に久保選手のようなアタッカーには、爆発的なスピードや俊敏性を生み出す「速筋線維」が重要になります。彼のふくらはぎは、余分な脂肪が少なく、質の高い筋肉で構成されているため、細く見えても、一瞬の動き出しやステップワークで大きなパワーを発揮できると考えられます。
アキレス腱の長さも影響
また、ふくらはぎが細く見える要因の一つに、アキレス腱の長さが関係している可能性があります。一般的に、アキレス腱が長いと、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋)の位置が高くなり、足首周りがシャープに見えます。
これはバネのある動きに適した身体的特徴であり、彼の俊敏なプレーを支える一因となっているのかもしれません。したがって、「ふくらはぎが細い」という見た目の印象だけで、彼のフィジカルを判断するのは早計であり、その裏には機能的な利点も隠されているのです。
スペインで痛感したフィジカルの重要性
日本で若くして才能を開花させた久保建英選手が、次なるステップとして選んだのは、世界最高峰のリーグの一つであるスペインのラ・リーガでした。しかし、そこで彼が直面したのは、これまで経験したことのないレベルのフィジカルコンタクトの激しさです。
テクニックだけでは通用しない場面が数多く存在しました。例えば、ボールを保持しようとしても、屈強なディフェンダーに体を寄せられるだけで簡単にボールを奪われてしまう。
あるいは、ドリブルで仕掛けようとしても、巧みなショルダーチャージで進路を阻まれる。このような経験を通じて、彼は自身のテクニックを最大限に活かすためには、それを支える強靭なフィジカルが不可欠であることを痛感したのです。
このスペインでの経験は、彼にとって大きな転機となりました。ただ単に体を大きくするのではなく、サッカーのプレーに直結する「使える筋肉」を身につける必要性を強く認識させました。この気づきが、後の計画的かつ効果的な肉体改造への強いモチベーションに繋がったことは間違いありません。
過酷な筋トレメニューで肉体を改造
フィジカルの重要性を痛感した久保建英選手は、そこから本格的な肉体改造に着手します。彼の変化は、単に試合をこなす中で自然に起こったものではなく、明確な意図を持ったトレーニングの賜物です。
報道などによると、彼は専属のトレーナーと共に、科学的根拠に基づいた緻密なトレーニングプログラムを実践しているようです。その内容は、単に重いウェイトを上げるだけでなく、サッカーの動きに直結する機能的なトレーニングが中心となっています。
例えば、体幹を安定させながら四肢を動かすトレーニングや、爆発的なパワーを生み出すためのプライオメトリクストレーニングなどが含まれていると考えられます。
シーズン中も、コンディションを維持しつつ筋力を向上させるために、試合のスケジュールに合わせてトレーニングの強度や内容を細かく調整しています。このような地道で過酷な筋トレを継続した結果、かつての華奢なイメージを払拭し、当たり負けしない強靭な肉体を手に入れるに至ったのです。
ベンチプレスで鍛え上げた上半身の強さ
サッカーは足元の技術が注目されがちですが、現代サッカーにおいて上半身の強さは非常に重要な要素です。久保建英選手もその点を理解し、ベンチプレスに代表される上半身のウェイトトレーニングに力を入れていることが、その肉体からうかがえます。
上半身、特に胸や肩、腕の筋肉を鍛えることは、ピッチ上での様々な局面で有利に働きます。最も分かりやすいのが、相手選手との競り合いです。ボールをキープする際に、腕や肩を使って相手をブロックすることで、自分の懐にボールを収めるスペースを作り出すことができます。これにより、プレッシャーを受けても安易にボールを失わなくなりました。
また、上半身の強さは体幹の安定にも繋がり、ドリブルやシュート時のフォームを崩れにくくする効果もあります。力強い腕の振りは、ランニングスピードの向上や、シュート時のパワー増大にも貢献します。
ベンチプレスで鍛えられた厚い胸板は、単なる見た目の変化だけでなく、彼のプレーの質を一段階引き上げるための、論理的な肉体改造の結果なのです。
当たり負けしない体幹トレーニングの成果
久保建英選手のプレーを見ていて顕著に感じるのが、体幹の強さです。相手に寄せられても軸がブレず、倒れ込みながらも正確なパスやシュートを放つことができるのは、徹底した体幹トレーニングの成果に他なりません。
体幹とは、腹筋や背筋、腰回りなど、胴体部分の深層筋(インナーマッスル)を指します。この部分が安定していると、手足の動きがスムーズになり、全身で生み出したパワーを効率的にボールに伝えることが可能になります。
久保選手が行っている体幹トレーニングは、一般的な腹筋運動のような単純なものではなく、不安定な足場の上でバランスを取るトレーニングや、体を捻る動作を取り入れた複合的なメニューが中心であると推測されます。こうしたトレーニングによって、彼は以下のようなメリットを享受しています。
- ボディバランスの向上: ドリブル中に相手からチャージを受けても体勢を維持できる。
- プレーの安定性: どのような体勢からでも、正確なキックやパスを繰り出せる。
- 怪我の予防: 身体の軸が安定することで、関節への負担が軽減される。
この強靭な体幹こそが、彼のテクニックを世界トップレベルで発揮するための、揺るぎない土台となっているのです。
久保建英の筋肉がプレーに与える影響
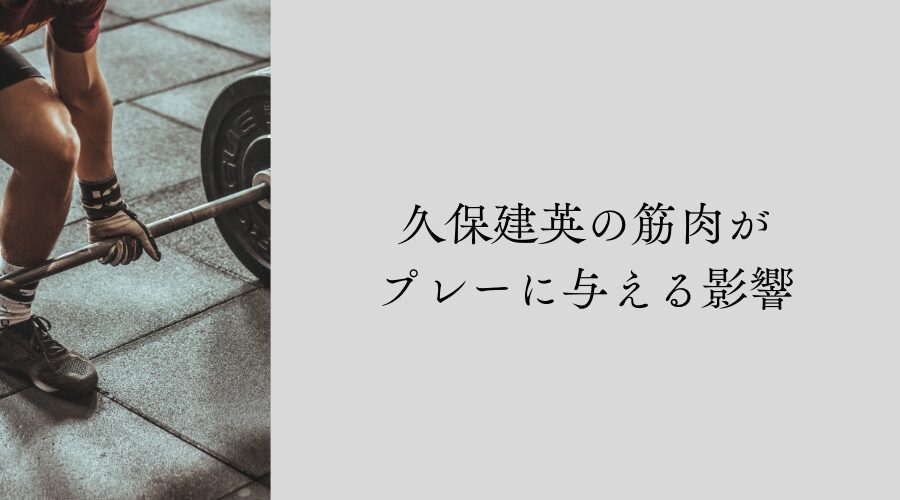
- 向上した身体能力がプレーの質を変えた
- 相手を圧倒する驚異の身体能力とは
- 爆発的なキック力を生む下半身の秘密
- ドリブルを支える下半身の安定感
- アジリティと筋肉の理想的なバランス
- まとめ:久保建英の筋肉は進化を続ける
向上した身体能力がプレーの質を変えた
肉体改造によって向上した身体能力は、久保建英選手のプレーの質を劇的に変化させました。以前はテクニックを駆使して相手を「かわす」プレーが中心でしたが、現在はフィジカルを活かして相手を「制圧する」プレーも可能になっています。
この変化を分かりやすく示すために、デビュー当時と現在のプレーを比較した表を見てみましょう。
| プレー項目 | デビュー当時 | 現在(肉体改造後) |
|---|---|---|
| フィジカルコンタクト | 接触を避ける傾向があった | 積極的に体を当て、ボールを保持できる |
| ドリブルスタイル | 俊敏性を活かした細かいタッチが主 | パワーを兼ね備え、直線的な突破も増加 |
| シュート | 技巧的なコース狙いが中心 | 力強いミドルシュートも武器になった |
| 守備への貢献 | チェイシングが中心 | ボール奪取能力が大幅に向上 |
このように、全てのプレーにおいて、フィジカルという新たな武器が加わったことが分かります。これにより、プレーの選択肢が格段に増え、相手ディフェンダーにとっては、より予測しづらく、厄介な存在へと進化したのです。テクニックとパワーを高いレベルで両立させたことが、彼のプレーを新たな次元へと引き上げました。
相手を圧倒する驚異の身体能力とは
久保建英選手が見せる驚異の身体能力は、単なる筋力だけではありません。サッカーという競技に特化した、複数の要素が組み合わさった能力です。
一つ目は「ボディバランス能力」です。前述の通り、強靭な体幹により、相手に強く寄せられても軸がブレません。これにより、密集地帯でもボールを失わずに前を向くことができ、次のプレーへの移行が非常にスムーズです。
二つ目は「アジリティ(俊敏性)」と「パワー」の融合です。筋肉を増やすとスピードが落ちるという懸念もありますが、彼はトレーニングによって、筋肉量を増やしながらも、初速の鋭さや方向転換の速さを維持、あるいは向上させています。静止した状態から一瞬でトップスピードに乗る能力は、相手ディフェンダーにとって大きな脅威となります。
そして三つ目は「プレーの持続力」です。試合終盤になっても運動量が落ちず、攻守にわたって走り続けられるスタミナも、彼の身体能力の高さを物語っています。これらの要素が組み合わさることで、90分間を通して相手を圧倒し続けることが可能になるのです。
爆発的なキック力を生む下半身の秘密
久保建英選手の左足から放たれるシュートは、年々威力と精度を増しています。この爆発的なキック力を生み出しているのは、徹底的に鍛え上げられた下半身の筋肉に他なりません。
キックという動作は、足だけで行っているわけではありません。まず、地面をしっかりと踏み込む軸足の安定が不可欠であり、これには臀部(お尻)や大腿四頭筋(太ももの前側)の強さが求められます。久保選手は、この軸足が非常に安定しているため、どんな体勢からでも力強いキックを放つことができます。
次に、ボールを蹴る側の足の動きです。ここでは、股関節を起点として、大腿四頭筋が振り子の役割を果たし、ボールインパクトの瞬間には膝下が鞭のようにしなることで、ボールに爆発的なエネルギーを伝えます。
この一連の動作をスムーズかつパワフルに行うためには、太ももだけでなく、ハムストリングス(太ももの裏側)や腸腰筋(股関節の深層筋)といった、下半身全体の筋肉が連動して機能することが大切です。
彼の肉体改造は、このキックに必要な全ての筋肉群を強化し、その結果として、ワールドクラスのキック力を手に入れることに繋がったのです。
ドリブルを支える下半身の安定感
久保建英選手の最大の武器の一つであるドリブルも、下半身の安定感によって支えられています。彼のドリブルは、ただ速いだけでなく、相手のチャージを受けてもバランスを崩さない力強さを兼ね備えています。
この安定感の源は、低く保たれた重心と、それを支える下半身の筋力です。特に、臀部や太ももの筋肉が発達していることで、地面をしっかりと捉え、上半身のブレを最小限に抑えることができます。これにより、相手ディフェンダーは、ボールを奪おうと体をぶつけても、逆に弾き返されてしまうことさえあります。
また、細かいステップワークや急激な方向転換を繰り返すドリブルは、足首や膝の関節に大きな負担をかけます。
しかし、下半身の筋肉がこれらの関節を保護する役割を果たすことで、怪我のリスクを低減しつつ、アグレッシブな仕掛けを続けることが可能になります。テクニックとフィジカルが融合した彼のドリブルは、まさに下半身の安定感の賜物と言えるでしょう。
アジリティと筋肉の理想的なバランス
サッカー選手にとって、筋力トレーニングは諸刃の剣になる可能性があります。やみくもに筋肉を増やすと、体重が増加し、持ち味であるスピードや俊敏性(アジリティ)が損なわれる危険性があるためです。しかし、久保建英選手は、この課題を見事に克服し、パワーとアジリティの理想的なバランスを保っています。
これを実現できた理由は、彼のトレーニングが「量より質」を重視し、サッカーの動きに直結する機能的な筋肉を鍛えることに特化しているからです。
例えば、重いウェイトを持ち上げるだけでなく、素早い動きの中で体をコントロールするトレーニングや、瞬発力を高めるトレーニングを組み合わせることで、筋力とスピードの両立を図っています。
この絶妙なバランス感覚が、彼のプレーの最大の特徴です。大柄な選手に当たり負けしないパワーを持ちながら、小柄な選手のような鋭いターンやステップワークもできる。この「パワーとアジリティの両立」こそが、彼を世界でも稀有な存在にしており、相手チームが対応に苦慮する最大の理由なのです。
まとめ:久保建英の筋肉は進化を続ける
この記事では、久保建英選手の筋肉に焦点を当て、その進化の過程とプレーへの影響を解説してきました。最後に、本記事の要点を以下にまとめます。
- デビュー当時は華奢な体格でフィジカルが課題だった
- ふくらはぎが細く見えるのは機能的な筋肉の質や骨格の特徴によるもの
- スペインリーグの激しい当たりを経験しフィジカルの重要性を痛感した
- 専属トレーナーと共に計画的で過酷な筋トレを実践
- ベンチプレスなどで上半身を強化し競り合いに強くなった
- 体幹トレーニングの成果でプレー中のボディバランスが向上
- 肉体改造によりプレーの選択肢が格段に増えた
- テクニックだけでなくパワーでも相手を制圧できるようになった
- 強靭なフィジカルはプレーの質そのものを変えた
- ボディバランス、パワー、アジリティが高いレベルで融合している
- 鍛え上げた下半身が爆発的なキック力を生み出している
- 軸足の安定がシュートの威力と精度を高めている
- 下半身の安定感が当たり負けしないドリブルを支えている
- 筋肉と俊敏性の理想的なバランスを維持している
- 久保建英の筋肉は今もなお進化の過程にある